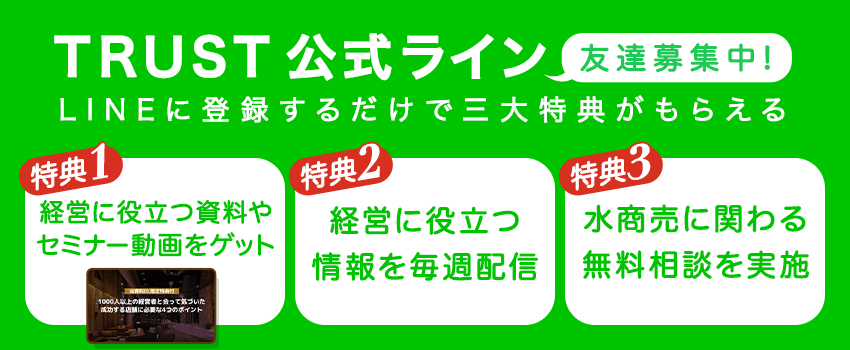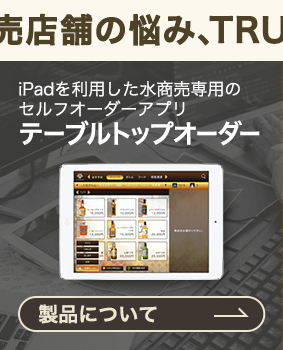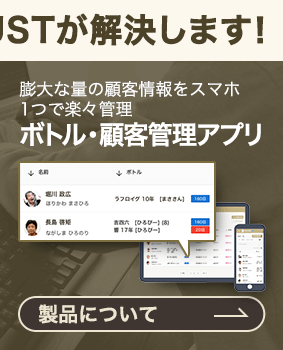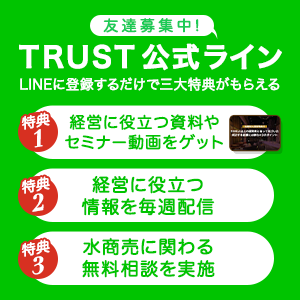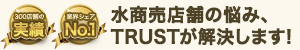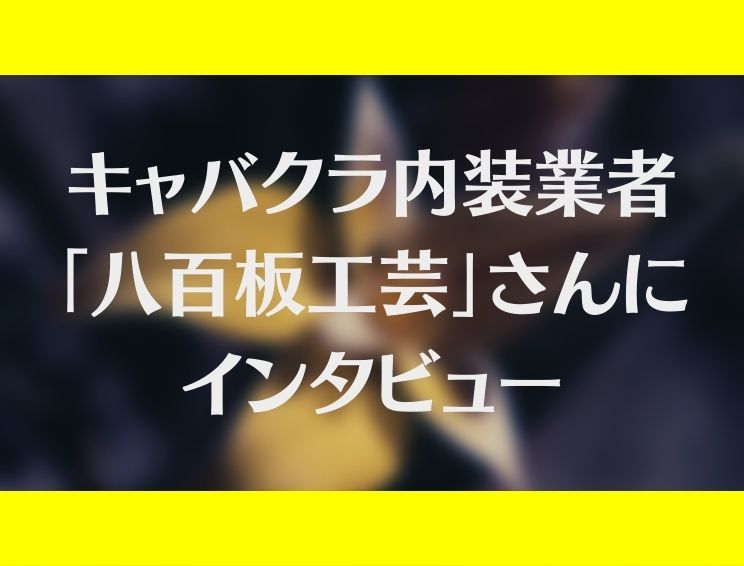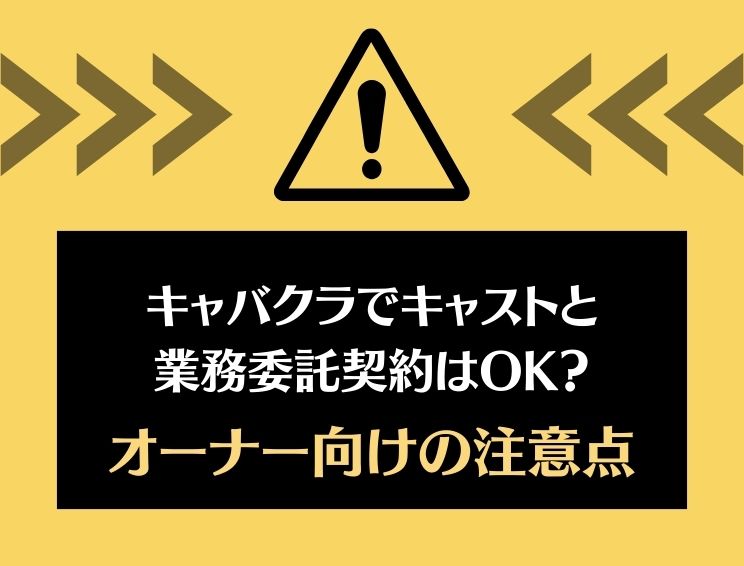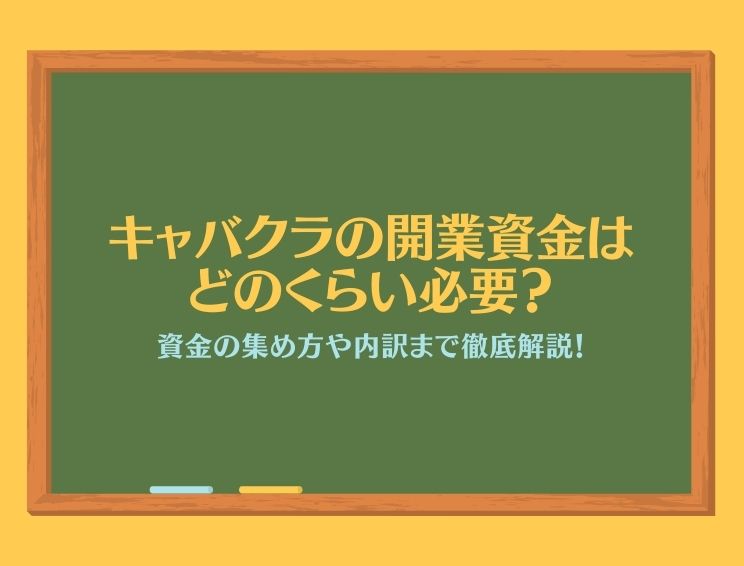目次
本記事をご覧の方は、以下の疑問をお持ちではありませんか?
- キャバクラで今もタバコって吸えるの?
- 喫煙ルールが変わったって聞いたけど、何を守ればいい?
喫煙に関するルールは、2020年の法改正以降、キャバクラにも厳しく適用されるようになりました。
一見タバコOKに見える店舗でも、実は条例違反や罰則対象になるケースも珍しくありません。
知らずに違反すれば、最大で50万円以下の罰金が科される可能性も。
喫煙のルールは、お客様・キャスト・黒服すべてに関係する重要な問題です。
本記事では、キャバクラでのタバコに関するルールと対応策を以下のように解説します。
- キャバクラでの喫煙ルールと規制の背景
- 合法的に喫煙可能な店舗の条件
- キャバ嬢・黒服・お客様への対応とマナー
喫煙対応は“空気を読む”だけでは通用しない時代です。
トラブルや罰則を未然に防ぐために、ルールと現場対応を整理しておきましょう。
キャバクラでタバコが吸えなくなった理由とは?

キャバクラが原則として禁煙になったのは、受動喫煙防止のための法改正が背景にあります。
特に2020年4月に施行された「改正健康増進法」により、飲食を伴う店舗は屋内禁煙が義務化。
キャバクラも例外ではなく、その対象となっています。
「昔は当たり前だった」では通用しない現代の喫煙ルール。
その背景には、以下のような要因が挙げられます。
それぞれの要因を、以下で詳しく見ていきましょう。
① 受動喫煙による健康被害が社会問題に
近年、受動喫煙が健康に及ぼすリスクが強く認識されるようになり、国全体で規制が強化されました。 特に飲食業界では、お客様・従業員問わず煙を避けたい人が増加しています。
- キャストやスタッフの健康被害が問題視
勤務時間中に常にタバコの煙を吸う環境は、職場として健全とは言えないとされる - 非喫煙者の来店ハードルが下がる
禁煙化により、今まで来店を避けていた層の集客も期待できる
これらの健康志向の高まりが、キャバクラ業界にも無視できない影響を及ぼしています。
② 改正健康増進法による法的義務
2020年に全面施行された「改正健康増進法」により、多数の人が利用する施設は原則、屋内禁煙とされました。 キャバクラは飲食サービスを提供する施設であり、法律の適用対象です。
- 喫煙専用室がない場合は完全禁煙
違反した場合、最大で50万円以下の罰金が科される可能性がある - 20歳未満の立ち入り制限
従業員・お客様問わず、喫煙エリアに未成年が立ち入るだけで違法となる
努力義務だった以前と異なり、現在では「違反=罰則」という厳格な規制になっています。
③ 東京都や大阪府ではさらに厳しい独自条例
東京・大阪など一部の自治体では、国の法改正よりもさらに厳しい独自ルールが導入されています。
- 東京都:従業員がいる店舗は原則禁煙
東京都では「東京都受動喫煙防止条例」が施行されており、従業員を雇っている店舗は全面禁煙 - 大阪府:30㎡を超える飲食店舗は禁煙(2025年4月施行予定)
大阪府では、店の広さと従業員の有無に応じて禁煙義務が強化される
東京都のケースでは、国の「改正健康増進法」では飲食店全体の45%が規制対象なのに対し、条例によって約84%の店舗が禁煙対象に拡大されています。
また東京都では、以下の2つの法制度を両方押さえておく必要があります。
- 国の法律 → 改正健康増進法
- 東京都の条例 → 東京都受動喫煙防止条例
従業員が一人でもいれば「例外なしで禁煙対象」になるため、キャバクラのようにスタッフが常駐する業態は原則禁煙と認識すべきです。
詳しくは、以下の公式ページも参考にしてください。
厚生労働省|受動喫煙対策
④ 従業員の働く環境を整える流れ
キャバクラに限らず、ホスピタリティ業界全体で労働環境の改善が求められている流れも大きな要因です。
禁煙にすることで、店舗にとって以下のメリットがあります。
- 非喫煙者のキャスト確保
- 黒服・ホールスタッフの健康配慮
これからの時代、店舗の魅力は「接客力+環境整備」。
その意味でも、喫煙ルールの見直しは避けて通れない課題といえるでしょう。
例外的に「喫煙OKなキャバクラ」とは?

現在の法律下でも、一定の条件をすべて満たすキャバクラは、店内での喫煙が許可される例外となります。
ただしその条件はかなり厳しく、実際に該当する店舗は少数派です。
「うちはまだ吸えるから大丈夫」と油断すると、罰則の対象になるリスクも。
どのようなケースで喫煙が認められるのか、以下の条件を確認しましょう。
これら3つすべてに該当しなければ、店内喫煙は原則禁止となります。
① 2020年3月31日以前から営業していること
この条件は、改正健康増進法の「経過措置」に基づいた例外規定です。
- 法施行前に開業していた店舗のみが対象
- 営業実態の証明が求められるケースも
2020年4月1日以降に開業したキャバクラは、いかなる理由があっても屋内喫煙は不可。
営業許可証や開業届など、開業日を証明する書類が必要になる場合もあります。
② 資本金または出資の総額が5,000万円以下
これは「中小規模飲食店」として、例外措置が適用されるかどうかの基準です。
法人登記時の資本金をもとに判断されるため、過去に資本金を増資していた場合は、例外対象から外れる可能性があります。
また、個人事業主でも「出資額」として扱われ、融資等を含めた出資総額が対象となるため、実質的な資金規模も要確認です。
③ 客席面積が100㎡以下であること
この条件が最もネックになりやすく、100㎡(約30坪、64畳)を超えると即アウトです。
- カウンター+BOXで15卓未満が目安
- バックヤードやキッチンは面積に含まれない
小型店でなければ、面積条件をクリアするのは難しいでしょう。
「客席部分のみ」が判断基準となるため、図面による正確な確認が必要です。
キャバクラ経営者が取るべきタバコ対策とは?

受動喫煙防止法や各自治体の条例により、キャバクラ経営にも明確な「喫煙対応」が求められる時代になりました。
曖昧なルールのまま営業を続けていると、罰則・行政指導・スタッフ離職・顧客離れと、あらゆる面でリスクを抱えることになります。
キャバクラ経営者として、以下のような実務的対応を検討しておくべきでしょう。
① 店内ルールを明文化し、スタッフと顧客に周知する
まず重要なのは、タバコに関するルールを明確に決め、店内とスタッフに徹底して共有することです。
- 「紙タバコは禁止/電子タバコはOK」など、明確な指針を作る
- ポスター・卓上POPなどで顧客にもわかるよう表示
トラブルは、「何がOKで、何がNGか」が曖昧なときに起きます。明文化されたルールが、スタッフと顧客の安心感につながります。
② 喫煙専用室の設置を検討する
全面禁煙が厳しい場合、喫煙専用室の設置が現実的な選択肢となります。
- 仕切り・換気設備・ドア付きなど、基準を満たした空間であれば設置可能
- 喫煙室内では飲食ができないため、構造設計が重要
初期コストはかかるものの、顧客満足と法令順守を両立できる最も確実な方法です。
③ キャバ嬢・黒服への教育を徹底する
タバコに関するトラブルを防ぐには、スタッフが法律や店内ルールを理解して行動できるかがカギになります。
- 「お客様のタバコに火をつける」行為も法律違反になり得ることを共有
- 新人教育マニュアルに喫煙ルールを明記する
スタッフ一人の判断ミスが、店舗全体にダメージを与える時代です。教育とマニュアル化でリスクを最小限に抑えましょう。
④ 行政の窓口・専門家との連携で最新情報を把握
法律や条例は年々アップデートされています。特に、大阪府の受動喫煙防止条例(2025年4月施行)など地域による差が大きいため、行政窓口と連携をとることが重要です。
- 管轄の保健所・自治体に事前相談を行う
- 税理士や社労士などと定期的に法令確認を実施
「知らなかった」では済まされないリスクがあるからこそ、プロの知見を活用しましょう。
キャバクラにおける喫煙マナー&接客時の対応

店舗ルールを整えても、実際にお客様と接するキャバ嬢や黒服の振る舞い次第で店の印象は大きく変わります。
特に、喫煙に関してはタバコを吸う人・吸わない人のどちらにも配慮することが求められます。
キャスト・黒服が心得ておくべきマナーや気配りを、以下に整理しました。
① タバコに火をつける時のスマートなマナー
キャバクラでは、お客様のタバコに火をつける行為が接客の一環として行われる文化があります。
ただし、法律やマナーの観点からも注意が必要です。
- 必ず「火をおつけしてもよろしいですか?」と確認 無言で火をつけるのはNG。丁寧なひと言が印象を左右します。
- 自分の手元で火をつけ、距離をとってスマートに点火 お客様の顔や手に近づけすぎないよう注意しましょう。
また、自分のライターではなく、お客様のライターを使う方が好まれるケースもあります。お客様の持ち物を丁寧に扱う配慮も評価されるポイントです。
② 灰皿交換は「早すぎず、遅すぎず」が鉄則
快適な空間を保つため、灰皿交換は重要な接客要素のひとつです。
ただし、頻繁に交換しすぎると会話の妨げになることも。以下のタイミングを意識しましょう。
- タバコ2~3本分の吸い殻がたまったら交換
- 灰皿交換時は、テーブルをまたがず丁寧に
- お客様の会話や食事を妨げないよう配慮
また、「交換しなくていいよ」と言われても、一度は「すぐに新しい灰皿をご用意しますね」とお伺いするのが接客の基本です。
③ 非喫煙者の席では「タバコに触れない」気遣いが必要
お客様が非喫煙者だった場合、タバコや煙への配慮が一層求められます。
キャストや黒服が喫煙者であっても、以下の点を徹底しましょう。
- 接客中の喫煙は一切NG(たとえ許可を得ても避けるのが無難)
- 煙の流れに気を配り、空調の調整も提案
- 灰皿が必要ない場合は、事前に下げておく
また、電子タバコや加熱式タバコであっても、においや蒸気を嫌うお客様が多いため、基本的には「吸わない接客」が推奨されます。
キャバクラにおける喫煙ルールに関するよくある質問(QA)
Q1: キャバクラでは今もタバコを吸っていいのですか?
現在でも喫煙可能なキャバクラは存在しますが、
「喫煙目的室」や「喫煙可能店」としての届出が必要です。
店内全体で喫煙を認めるには、一定の条件を満たす必要があるため、事前確認が重要です。
Q2: 喫煙ルールが変わったと聞いたけど、何を守ればいいですか?
2020年の改正健康増進法により、飲食店での喫煙ルールは大きく変わりました。
喫煙専用室の設置、20歳未満の立入制限、標識掲示などが義務付けられており、
違反すると罰則が科される場合もあるため注意が必要です。
Q3: 店内を喫煙可能にするにはどんな手続きが必要ですか?
各自治体の保健所への届出が必要です。
また、「喫煙可能店」「喫煙目的室」など用途に応じた区分での申請が求められます。
届け出後、入口への標識掲示も義務です。
Q4: 非喫煙者の従業員を守るためにはどうすればいいですか?
従業員の健康を守るには、喫煙エリアと非喫煙エリアを完全に分ける、
空気清浄機の設置や休憩スペースの分離などの対策が有効です。
特に、20歳未満の従業員を喫煙エリアに立ち入らせることは禁止されています。
Q5: 電子タバコ(加熱式タバコ)なら自由に吸えるの?
電子タバコも法的には「喫煙」と同じ扱いです。
紙巻きタバコとの違いに関係なく、同様の規制が適用されるため、
誤ってルールを緩く捉えないよう注意が必要です。
まとめ:キャバクラのタバコルールは「知らなかった」では済まされない
2020年の法改正以降、キャバクラにおける喫煙ルールは大きく変わり、今や店内での喫煙には厳しい制限がかかる時代となりました。
以下の点を押さえておくことが、店舗運営や接客でトラブルを避ける鍵になります。
- 原則、店内での喫煙は禁止(喫煙専用室の設置が必要)
- 一部例外あり:小規模・資本金5000万円以下・既存店など
- 東京都などはさらに厳しい条例が施行中
- 電子タバコにも独自ルールやマナーが必要
- キャスト・黒服も「におい」「印象」対策が重要
店舗ルールの明確化とスタッフへの共有を徹底し、お客様にとって快適な空間を提供しましょう。
今後さらに規制が強化される可能性もある中、柔軟な対応力と正確な知識がキャバクラ経営の必須条件です。